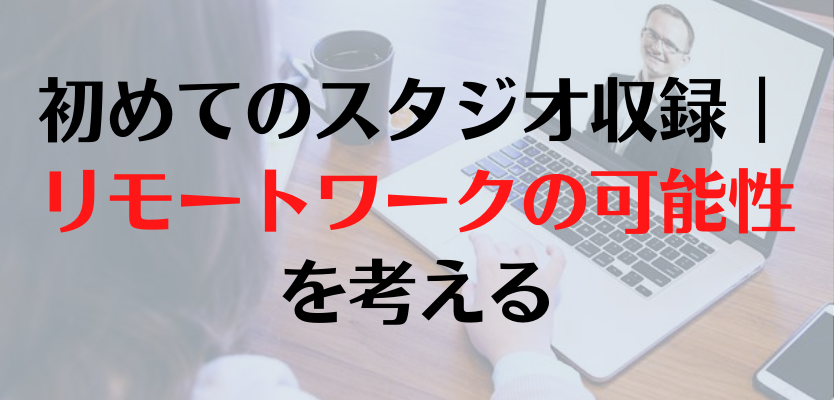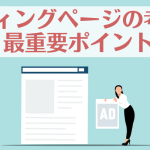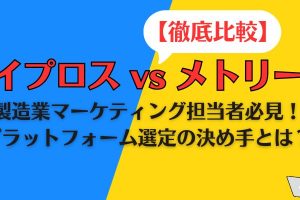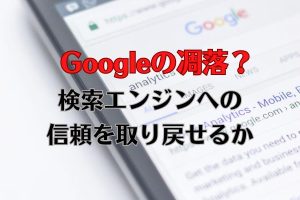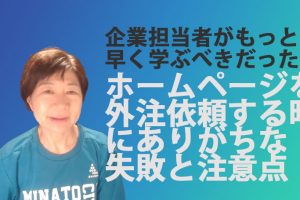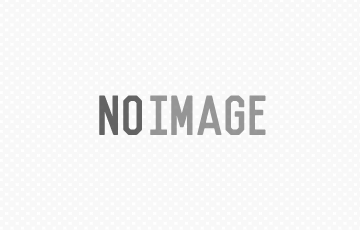この2年間コロナでリモートワークが進みました。
ですが、蔓延防止措置期間がおわり、御社では通常出社にもどっていませんか?
リモートワークとか言うけど、やっぱりわが社では無理だし、集まった方が仕事やりやすいよ、とお考えではありませんか?
会社に集まるものを全面否定はしませんが、リモートワークの便利さを実感した社員の方からはリモートを継続してほしいという声が絶えないのも事実です。
- 我が社のような種類の仕事はリモートワークは、絶対無理
- 人は会って話すのが一番
- 合わないと「あうん」の呼吸がわからない
リモートワークと言っても限界はある、私もそう思っていました。
ですから、「スタジオ収録」という仕事を引き受けた時は、絶対リモートでは無理だと思っていました。とにかく収録のためには、どこかのスタジオに集まらないといけないと思い込んでしました。こんな感じのところですね。

ところがこれができたのです。リモートでのスタジオ収録。パートナーは神戸、私は東京。
ラジオの収録30分、無事オンエアされました。
やればできるもんだと思いました。自分の「常識」が覆った瞬間でした。
改めてリモートワークの可能性を感じました。
たいていの仕事はリモートでこなすことができると思います。しかしそれにはそれなりに準備が必要でした。
今日は、そもそも「スタジオ収録」というお仕事に協力することになった背景と、どうやってリモートの壁を乗り越えたのか、メリットとデメリットについてお話します。
1.この仕事の背景
そもそも、なぜ本業でもない「スタジオ収録」を引き受けることになったのか。
知人A氏が本を出版し、出版費用をクラファンで集めました。その協力の見返りとして「ラジオ出演権」を買ったからです。知人は小さなインターネットラジオ番組を持っており、その「ラジオ出演権」をクラファンで、寄付の御礼として出品したのです。寄付金額と御礼の中身が一番釣り合っていました。
A氏が神戸在住なのは知っていましたし、スタジオも神戸にあります。ですので正直、これはクラファンへの寄付であって「ラジオ出演権」は実現しなくてもいいや、という気持ちでした。
クラファンが終わって数カ月した後、神戸の知人から連絡がありました。
『僕も慣れてきたので、リモートでも「スタジオ収録」できるようになったんですよ。』
正直、ビックリしましたが、本当にできるのかしら、という好奇心からラジオ出演にOKしました。
2. リモートに向けての準備
ラジオ番組は30分。適当にやって時間に収まる訳がありません。
A氏の準備は入念でした。
まず、ざっくりの進行表をいただきました。挿入する音楽、分数まですべて網羅されています。
次に事前打合せです。そこで、あらかじめ大枠の流れの説明をいただき、質問したい項目を尋ね、その答えを出演者、つまり私から聞き出します。
出演者の回答がいささかまずい、という場合はアドバイスしてくれました。
この事前打ち合わせを経て、台本が出来てきました。
進行表はさらに詳細になっており、「基本としては、これをこの時間内に読んでください」というレベルまで文章にしてあります。こうして内容が詰められていきました。
3. 「スタジオ収録」の本番
本番収録の日がきました。初めてだったので、誰もみていないのに緊張しました。ラジオですので顔は見えないのでそこは安心。メイクや見た目は普段通りです。
収録はZoomで行います。A氏の神戸と東京をつなぎ、Zoomでお互いの顔をみながら、進行表に沿って進めます。タイムキーピングが肝だとのお話でした。
A氏の司会進行も慣れたもので、盛り上げるところとか音楽いれるところとか、堂に行ったものでした。質問とか笑いとかをいれながら、番組が進行します。あっという間に30分の本番収録は終わりました。
この収録が、1週間後にラジオ番組で放映され、私は生まれて初めての「ラジオ番組出演」を果たしたのでした。
4. リモートによるメリット・デメリット
リモート環境で「スタジオ収録」という特殊なやり方をやってみた経験者としてのメリットとデメリットはこんな感じです。
1 メリット
- 圧倒的に低コスト。リアルなら必要な往復時間、費用がかからない。
- 遠方からのゲストを気軽に招待できる。
- ラジオ出演の垣根が下げられる。
2 デメリット
- 進行表の準備に時間がかかる
- 細かく事前に決めておけば失敗はないがが、アドリブによる意外性や面白味には欠ける。
- リアル出張で味わえる観光気分はなし
とはいえ、2の進行表の準備に時間がかかるというデメリットは、出演者が慣れていればかなりの部分、回避できると思います。
今回の出演者である私はド素人だったため、詳細な進捗表が必要でしたが、「喋りのプロ」や慣れた方なら、リモートで十分対応できると思いました。
リアル出張がないので観光気分が味わえないのは、仕方ないですね。
5. まとめ
いかがだったでしょうか
ラジオ番組の収録は、スタジオに集まってしかできない、と思い込んでいましたが、入念に準備していただいて、意外と簡単に30分のスタジオ収録は終わってしまいました。
人には無意識に持っているこれまでの「思い込み」があります。
ところが、「リモートでやる」と決めると、どうすればできるかを考えます。すると、それなりに知恵が出てくるものです。
そして実際にやってみて初めて「こうすればできる」と理解できます。一度やってみると、二度目はさらに簡単です。
Techや便利なアプリのおかげか、できないと思い込んでいたことが簡単にできる、ということは多くなっているように思います。
日本企業のリモートワークも、こういう状態ではないでしょうか。
「やってみたけど上手く行かない」という会社が多いのは、無意識に「リモートはリアルの代わり」と考えているからではないかと思います。
「リモートでやる」と決めてそのために、何をすれば良いのか、白紙から組み立てれば、会社の仕事はたいていのことはできると確信しています。
「あうん」の呼吸がないとできない「スタジオ収録」だってできたのですから。
「リモート化」ということは、仕事の目的を定義し、進め方や組み立てを白紙から変えるということです。その定義をした中で、集まることが必要な仕事ならばオフィスに集まればよいのです。
改めて、リモートワークには仕事のやり方を変える大きな可能性が秘められていると思いました。