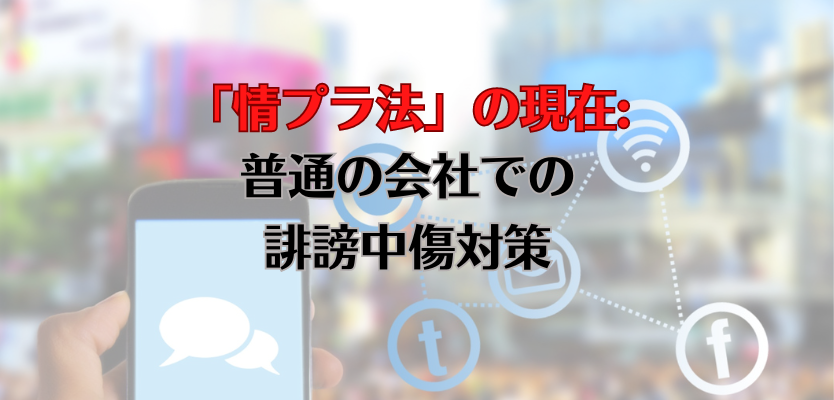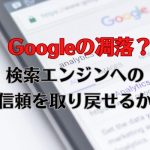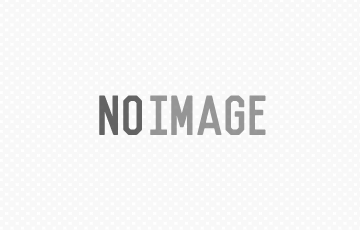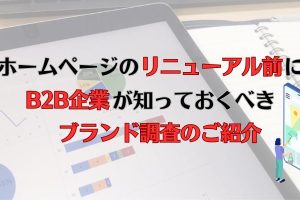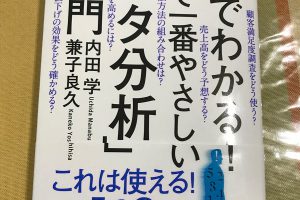情プラ法という言葉をご存知でしょうか。
正式には「情報流通プラットフォーム対処法」と言います。
ついこの間まではプロバイダ責任制限法と言われました。
ご存知ない方でもZOZOの創業者前沢友作氏がメタを訴えていることはお聞きになったことがあると思います。
SNSはやっていないから、そんなことは関係ないと思っておられる会社は多いと思います。
しかしSNSで自社に全く言われのない誹謗中傷が書かれた時はどうすればいいでしょうか。
ここでは、日本の現在の法律はどうなっているのか、海外に比べてどうなのか、実際にウェブ業界以外の会社が誹謗中傷を受けた時にはどのように対策すればいいのかということについてまとめてみました。
ちなみに私自身はコミュニティの運営サイトをしている会社に勤務したことがあります。
悪意のある書き込みのチェックというコミュニティの維持運営がどれほど大変なものかも理解しているつもりです。
しかし、この記事の中では誹謗中傷を書き込まれた側の立場に立って記事を書いています。
情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)とは
情報流通プラットフォーム対処法(以下「情プラ法」と記載)とは、元々はプロバイダ責任制限法と言われていたものです。
プロバイダ責任制限法を改正し、2024年5月に可決・成立しました。1年以内に施行される予定です。
情プラ法の対象者は「大規模特定電気通信役務提供者」です。
「大規模特定電気通信役務提供者」とは、大規模特定電気通信役務を提供する者として、総務大臣に指定された事業者で、一定以上のアクティブユーザーを抱える大規模プラットフォーム事業者です。
プロバイダ責任制限法と情プラ法の違い
では、従来のプロバイダ責任制限法と、大きく変わった点は、大規模プラットフォーム事業者に次のような義務が課されることになったことです。
- 削除申し出窓口の整備・公表
- 削除申し出への迅速な対応
- 削除基準の明確化
- 削除後の発信者への通知
誹謗中傷などの違法または有害な情報の削除義務がプラットフォーム側に課されることになりました。
事業者には十分な知識を持った人材の配置や、削除依頼があった場合は一定期間内(原則1週間程度)で投稿を削除するか判断し、依頼者へ通知することなども求めています。
法律の主旨として、ネット上の誹謗中傷などの有害情報の迅速な削除と被害者保護を目的としたものです。
情プラ法が改正された理由
これは悪質な誹謗中傷の事例がここ10年間ほど多発していたという背景があります。
2020年、プロレスラーの木村花氏がSNSに誹謗中傷を書き込まれ、自殺した事件があります。この時、書き込みをした側の男性2人が侮辱罪で書類送検されましたが、1名は科料9000円の略式起訴で終わっています。
最近では、堀江貴文氏とZOZO創業者の前沢友作氏が、無断で画像を使われ、株式投資のアドバイスを得られるなどと偽った広告がメタに出稿されており、実際に詐欺被害が出ています。堀江氏は1年以上前から広告掲載停止を求めていますが、対応されていません。
このような事情からプラットフォーム側に削除申請された書き込みについては削除義務を負わせるということは一つの大きな進歩だったと思います。
情プラ法の効果
では、この法律ができたおかげで、削除依頼をすればプロバイダーが健全なネット環境を維持してくれるというものでしょうか。
残念ながらそこまでは期待できないと思います。
プロバイダー側は、削除申出を受けた日から14日以内の総務省令で定める期間内に速やかに削除しなくてはいけませんが、その間はその書き込みは放置されます。
そして情プラ法は大規模事業者に対して、インターネット上における不適切な投稿への削除等の自主的な対応を促すものです。プラットフォーム側を対象とする法律であって、誹謗中傷をする人間の側に罰則を与えるという法律ではないのです。
また、学校裏サイトや小規模事業者の掲示板は情プラ法の対象ではありません。一定規模以上のユーザがないサイトであれば、誹謗中傷の書き込みへの対応は制限されていません。
つまり情プラ法というのは、ネット環境の維持のために、プラットフォーム側に責任を持ってやってくださいということを明文化したけれども、書き込みをするユーザへの処罰というところまでは踏み込んで規定してはいないのです。
ですので、ユーザーの態度や振る舞いが変わらなければ、どこまで行っても誹謗中傷は簡単になくならないでしょう。
海外での法規制
これは日本だけの問題ではありません。どの国もSNS上の誹謗中傷や悪意を持った書き込みをどう対処するのかということに頭を悩ませています。
インターネット上の表現の自由というのをどこまで確保すれば良いのかと、プロバイダーがどこまで責任を持つべきかというのは国によって考え方が分かれています。
米国
米国ではオンラインプラットフォーム事業者が、ユーザーが作成したコンテンツに対して削除する義務を負わないことを定めた通信品位法230条と呼ばれる法律があります。表現の自由を委縮させるリスクがあるということで、1997年以外、ほとんど改正されてきませんでした。
しかし2010年代以降、SNSが憎悪表現、偽情報、陰謀論の拡散に利用されることが増えたとして、プラットフォーム事業者の責任の所在について議論が進められています。
英国
1988年に「Malicious Communications Act」が成立しています。これは受取人に苦痛や不安を与える目的で手紙やその他の物品を送ることを禁止する議会法ですが、この法律が電子通信と書面による通信に適用され、ソーシャルメディアのユーザーを起訴し有罪判決を下すために使用されています。
オーストラリア
2021年オンライン安全法が制定されています。暴力的行為を促進・扇動するようなインターネット上の書き込みへのアクセスの遮断を要求できるようにするなど、ネット安全コミッショナー(eSafetyCommissioner)の権限を強化することを目的としています。
韓国
2007年に「制限的インターネット本人確認制度」で、いわゆる「インターネット実名制」に関して定めています。このインターネット実名制は、サイトの運営者が本人確認を行わない等これに違反した場合には、最高で3千万ウォン(約200万円)の罰金を科すと規定しています。名誉毀損行為について事実である場合には3年以下の懲役又は2千万ウォン(約133万円)以下の罰金、虚偽の事実の場合には7年以下の懲役を科す等、厳しく規定しています。
このように先進国でも対応はバラバラです。既存の法律を適用したり、新たな法律の枠組みをつくったりしていますが、米国のように、まだプロバイダーの責任を規定していない国もあります。
日本の法律も、何も規定がない状態よりは前進と言えるでしょうが、英国、オーストラリア等に比べるとプロバイダーに対する責任を定めただけという意味では不十分と言える状況です。
自社が被害にあった時は?
では自社が被害にあった時はどうすればいいでしょうか。
具体的には、言われのない製品の不具合をSNSで流布されたり、退社した社員が、会社の中傷をSNSで書き込まれたりした場合などです。
このような事態が起きる時、多くの場合は全く寝耳に水です。
自社でSNSの公式アカウントをもっていないから関係ないというのは幻想です。
利用するユーザーが多ければ多いほど、また関連会社を含めて関係する社員が多ければ多い程、このような誹謗中傷のリスクはあります。
そういった意味でもユーザーが幅広く日本全国で使われてるような製品を製造しているような企業は、まず自社防衛のためにSNSのアカウントを開設して運用すべきだと思います。
すぐに対応すべきこと
被害を受けたということを証拠を持って削除申請をしない限り、プロバイダーは対応はしてくれません。
では被害を受けたということをどうやって証明すれば良いのか。
具体的には以下のような資料を集めましょう。
- 誹謗中傷が行われた投稿のURLやスクリーンショット
- 投稿者のアカウント情報のURLやスクリーンショット
- 誹謗中傷による具体的な損害の証拠(営業損害を示す帳簿書類など)
- 誹謗中傷による精神的影響を示す資料(医師の診断書など)
誹謗中傷に関する被害を明確に示すためには、具体的な証拠の収集が非常に重要です。
ネットの場合、投稿や書き込みがすぐに削除されてしまったりすることもありますから、その場でスクリーンショットを撮って明確な被害状況を示す証拠を収集しておきましょう。
証拠を持ってプロバイダーに削除申請を行いましょう。
プロバイダーが迅速に動いてくれなかった場合
削除依頼をしたにも関わらずプロバイダーが迅速に動いてくれないというケースもありえます。
その場合には法的手段として被害届を警察に提出することになります。
しかし日本の警察がすぐに動いてくれるという保証はありません。
警察は具体的にその書き込みが、あきらかに「犯罪」に該当していたり、具体的な被害が発生している誹謗中傷については捜査を開始します。
しかしそうではない場合、例えば自社の製品の根拠のない書き込みが書かれたとかいうケースは、具体的な被害が出ていない限り、すぐに動いてくれるという保証はありません。
そのような場合にどうすれば良いかというと、加害者に対して明確に処罰を与えてほしいという意味を込めて告訴状を出すという手段があります。
被害届と告訴状は何がどう違うのかと言うと、被害届は犯罪事実を捜査機関に申告するものであるのに対し、告訴状は加害者に対する訴追・処罰を求めるための文書です。
誹謗中傷に対して警察に捜査を依頼し、加害者に法的な責任を取らせたい場合には、被害届に加えて告訴状を提出してください。
こういった法的な手段があるということと踏まえて、被害届を出したり告訴状を出したりという段階になったら、自社の企業弁護士の方等に早めに相談しましょう。
まとめ
自社が公式にSNSを運営していないから関係ないという考えは、今の時代では通用しなくなりました。
話題に上がるということは嬉しいことである反面、ネガティブな噂というのは警戒しなければいけません。
しかし残念ながらネガティブな噂というのは良い評判よりも早く伝わります。
そして今の20~30代はSNSで情報を拾って、ニュースを読む世代なのです。
自社の悪い評判が採用などに響くということも大いにありえます。
そういった意味も込めてB2Bであれ、B2Cであれ、自社のSNSアカウントを維持運営しておくことが必要になっていると思います。
[参考資料]