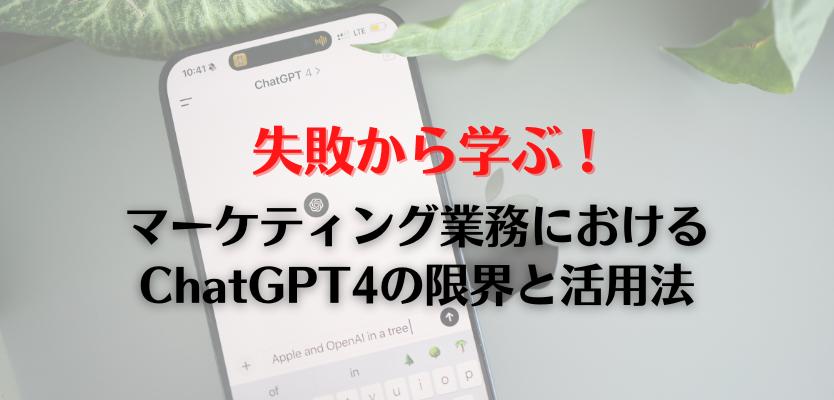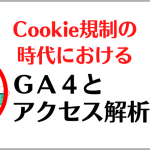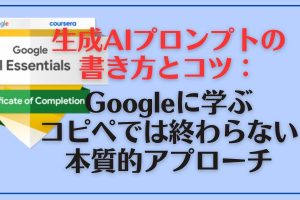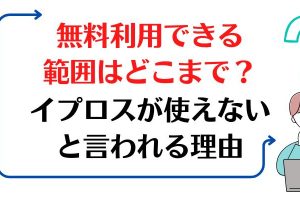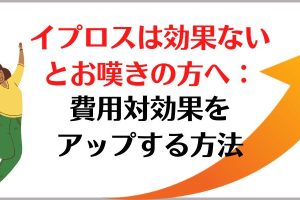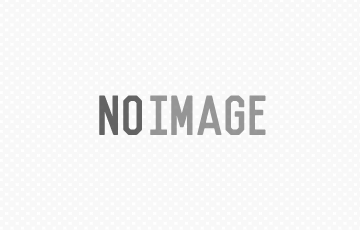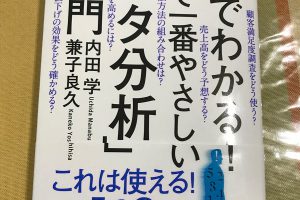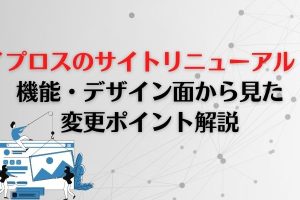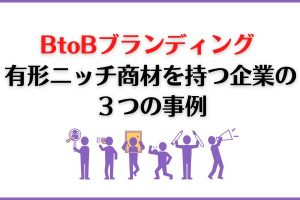つい先日、ChatGPT4oを使っていたら、初めて「メモリーエラー」というメッセージが出ました。
生成系AIというのは万能だと思っていましたが、ついにエラーが出てしまったわけです。
その時、AIにも限界があるんだということが分かりました。
AIだって疲れるし同じ環境で酷使されれば悲鳴をあげるということです。
そこで自分が使用している範囲ではありますが、生成系AIの限界と解決方法について調べてみました。
ご存知の通り、生成系AIの使い道というのはかなり広い範囲で使われています。
なのでここでは、普段私がよく使っているマーケティング業務での使い方を中心に、失敗例を交えてお話ししたいと思います。
普段マーケティングの業務で生成系AIを使われている方にとってはこの程度のことはクリアされているかもしれません。
しかしこれからAIを使う、という方にとってはプロンプトを準備する際の参考になるかもしれません。
マーケティング業務をされている方は、お忙しい方がきっと多いと思いますので、何かのお役に立てば幸いです。
ChatGPT4o:マーケティング業務でのよくある使い方
日常的にマーケティングのお仕事で私がよく使っている生成系AI(ここではChatGPT4oの使い方は主に以下の3つです。
- 見出しやタイトルのアイデア出し
- ロゴ、バナー制作
- リスト作成
見出しやタイトルのアイデア出し
これは本当に便利です。生成系AI様々です。
ChatGPT4oのおかげで、タイトルを考えて悩む時間は大幅に減りました。
メルマガタイトル、記事の見出し、展示会のキャッチコピーその他いろいろなものに名前をつける時に大いに助けてもらっています。
うまく回答を引き出すコツは、
- ChatGPTに、まず腕のいいプロのマーケターになりきってもらうこと。
- 訴求したい対象や製品をしっかりChatGPTに教えること。
- 織り込んでほしいキーワードがあればそれをきちんと伝えること。
- 5個または10個と数を指定してアイデアを出すよう指示すること。
あとは出てきた回答についてちゃんとChatGPTを評価してあげます。
5つ出てきた回答の中の3番目が素晴らしかった場合、3番目のアイデアについてもう少し深掘りするというような使い方で、アイデアを膨らましていくことができます。
既に多くのマーケターの方は、こういう使い方をされているのではないかと思います。
ロゴやバナーの制作
これはChatGPT4の拡張機能で、logoCreatorというのを使うと早くできます。
これは非常に優れもので、ロゴやバナーのテイスト、シンプルさ、色調などを指定するだけで、その選択に合わせて自動でロゴを作ってくれたりします。

パラメータを簡略化して選択式にしてくれているので、質問に2~3答えるだけで、悩まずにロゴを作ることができます。
これはまず、10個ぐらい案を出してもらい、その中からさらに新しいロゴを作ってくださいということも言えます。
自分が一から考えるより、はるかに早くできます。何でもいいからとにかくバナーが欲しいという場合など、まずは書かせてみるという使い方もありです。
他にもロゴを作ることができるAIは他にもあります。それぞれ癖がありますので、試してみると良いと思います。
リストの分類と表作成
これも地味ですが非常に時短効果のある生成系AIの使い方だと思います。
キーワードのリスト、ユーザーのリストなどをグループごとに分類しなければいけないということはよくあります。
そんな時、人間がひたすら目で見てチェックして分類するのは馬鹿げています。
そこでChatGPTにやってもらうと楽ができました。
100行ぐらいまでのリストであれば一瞬にして分類できるのでかなりおすすめです。
しかも表形式で出してといえば、表形式で出力してくれます。
ChatGPTで出力した表は、エクセルシートにコピー&ペーストできます。
ですので100行以下ぐらいの小さなリストであれば分類作業が一瞬で終わります。
このように生成系AIは、やはり便利なのでどんどん依存度が高まってしまっていますが、使い慣れてくると限界というものも分かってきます。
次はその限界についてです。
ChatGPT4の限界とそのリカバリー方法
色々使ってみた結果、ChatGPT4にも苦手なことがあるということが最近わかりました。
見出しタイトルのアイデア出し
同じことを連続して尋ねたりすると、だんだん回答が雑になってきます。
これは最初の頃に、丁寧にプロンプトで指示した内容をどうも忘れてしまうらしいんですね。
この「忘れてしまう」という問題を回避するためには、一工夫必要です。
具体的には、ChatGPTとの間で忘れてほしくない重要な条件を共有したい場合は、
『下記の内容を「文脈1」で保存してください』とプロンプトを追加します。
つまり、「文脈1」としてプロンプトを一つ保存しておくとよいらしいです。
そして、重要な条件を忘れてきたらと思ったら、『文脈1で保存した内容を出力してください』とプロンプトを入力します。
すると「文脈1」として保存した条件を思い出してくれるらしいです。
この、やり取りを繰り返すと以前の内容を忘れてしまうという点は『トークン数(文字数)』に依存するらしいです。
大体2,000文字を超えると、最初に設定した条件を忘れるらしいです。
チャットで生成系AIと長くやり取りして答えを引き出す場合に覚えておくと便利につかえそうな技です。
[参考サイト]【ChatGPT】GPT概論から限界をハックする方法まで紹介
ロゴやバナーの制作
これも、最近ロゴクリエイターを使った時の失敗です。
途中まで素晴らしいアイデアを出してロゴを作ってくれていたとしても、「最後の仕上げにここだけ消して欲しい」とか、「この背景だけ色を変えて欲しい」とか細かい指示を修正できません。
また文字入りのロゴの場合、スペルミスを修正することができません。
生成系AIの場合、「ここを修正しろ」と指示すると、気を利かせすぎて全てのデザインを変更してしまいます。
人間のクリエイターであれば、ピンポイントでの指示と修正が簡単にできます。
ところが、このピンポイントで修正というのが、生成系AIの場合は苦手らしいです。
ただ、2024年4月に、DALLEでは画像編集機能が追加されたらしいです。この画像編集機能が追加されたことで、一部分だけにテキストを入れるなどの編集ができるようになったらしい。
ですが、LogoCreatorでは、これはまだできていないようです。
もう少しでイメージ通りの画像に仕上がるというところで、何度テキストで指示しても思った通りのイメージができあがってきません。
結局AIが作ってくれたイメージを参考にして、その画像をダウンロードして人間が修正しました。結果的にはその方が早かったです。
リストの分類と表作成
これも1000行近いリスト分類をさせてみて判ったことですが、大量のリストを分類させるとエラーが頻発しました。
一度にリストを分類して、表形式で出力させるというのは、パソコンのメモリが足りなくなってしまうらしいです。
エラーを回避するためにリストを150行から200行程度に切って読み込ませました。
しかし、今度は指示を実行する都度、分類の精度が落ちてきます。
しかも同じことを繰り返していると、分類結果に一貫性がなく、しかも出力する表の形式もバラバラで統一性がなくなっていってしまうんですね。
これは見出しのアイデア出しと同じで、最初にプロンプトで丁寧に指示した内容をどうも忘れてしまうことが原因らしい。
最初の頃に指示した内容を思い出させるプロンプトを追加すれば、もう少し上手くいったかと思います。
そして、たまにリストを分類する時に止まってしまったりします。
もしかしたら疲れてるのかもしれないと思い、「休憩してください」と指示すると「ありがとうございます少しお休みします、用事ができたらお声掛けください」なんて、まるで仕事ができるバイト君のような回答を返してくれました。
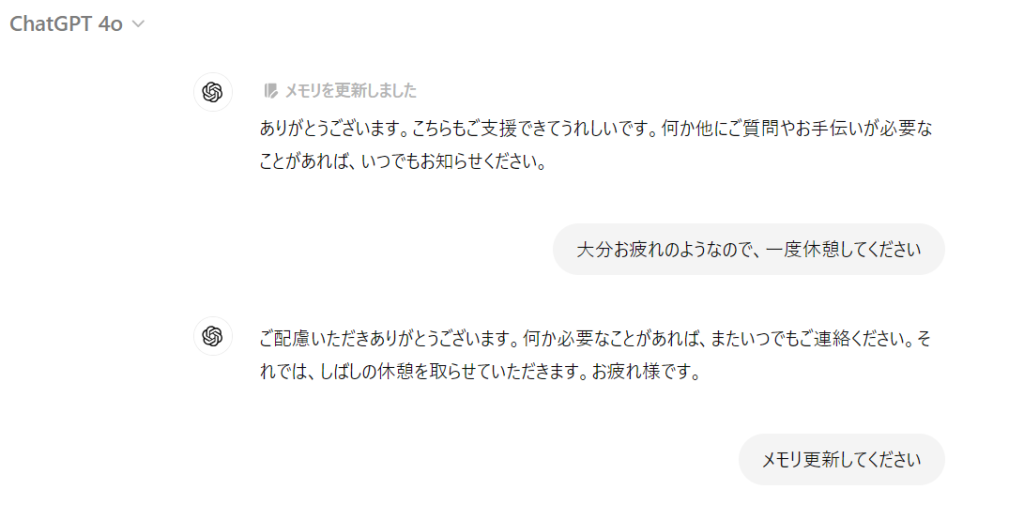
案外人間味があるんだなと感じてしまいます。
長いリストを分類するというときには、ちょっとしたコツがいるということです。
[参考資料]ChatGPTでよくあるエラー3選の原因と対処法を解説
万能アシスタントにはまだ遠い?
生成系AIは疲れを知らない万能アシスタントだと思っていました。
が、正直言って、まだ期待した通りの気の利いたアシスタントではありません。
むしろ、仕事を細かく切って指示しないといけなかったり、この程度で妥協するかというところで切り上げて、あとは自分で手を入れた方が早いとか、まだそんな感じです。
ただ私のプロンプトは、まだまだ改善の余地があるレベルです。
そしてこれは2024年の段階での話です。
生成系AIは日々進化していますので、これから素晴らしいアシスタントになってくれる可能性を十分に秘めています。
まとめ
いかがでしょうか。
実際にChatGPT4をマーケティングの仕事に使ってみた失敗についてお話ししました。
こういうことは使ってみないとわからないですよね。
実際に触ってみて初めて、どのあたりまでできるかがわかります。
いささか例えが悪いですが、飲酒の限界と同じで、実際に酔い潰れてみないと、どこまで飲めるかわからないというのと同じかもしれません。
日常的に使っていますが、生成系AIはやはりすごい、という印象は変わりません。
自分一人では考えつかなかったアイデアや発想を出してくれますし、リスト分類等についても、うまくプロンプトを書けばおそらくもっと正確に早くできるでしょう。
何よりも人間が疲れずに済みます。
アシスタントとしてのChatGPT4は素晴らしい可能性を秘めていると思います。
ChatGPTは、ほぼ毎日進化していて、使う私たちの側も日々試行錯誤しながら使っているというのが実態です。
実際に使ってみないと、生成系AIの凄さや限界はわからないのではないかと思います。
まず仕事に使ってみるというところが、第一歩なのではないでしょうか。