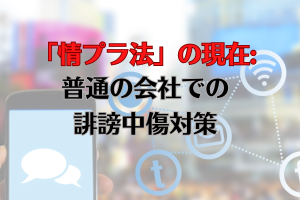橋田寿賀子さんが亡くなった。最高視聴率63%を叩き出した昭和朝ドラの金字塔。
数十年ぶりにドラマを見て、この番組が世界60ヵ国で放映され人気を得たのかが、分かった気がします。
あらためて令和の世の中に対しても訴えるものがあると思うので、私の個人的思い出も交えつつ整理してみたいと思います。
女の人生フルコース
このドラマは戦前、社会最底辺の小作人家庭に生まれた女性が、戦後スーパーの経営者として成功する物語。
だが、彼女の一生は不幸のオンパレード。
「なんであんなに可哀そうな女の子のお話を好き好んでみるのかわからない」と言った知人がいたが、まさしくその通りです。
奉公、結婚、いじめ、別居、死産、長男戦死、夫とは死別、シングルマザー。
ここまで”不幸のフルコース”を背負った女性は、80年代の当時では稀だったろうと思います。
ところがこの超可哀想なおしんを、80年代の当時の日本女性は共感を持って見続けたのです。
おしんのどこに共感するのか
おしんの何がそこまで共感を呼んだのでしょう。
おしんが生涯かけて求めたものは、当時の日本の女性達が求めてきたものーそして今の日本女性も求めているもの-自立と自己決定だったからだと思うのです。
橋田先生は、ドラマの中でいろんな役に、いろんなセリフで、おしんが生涯かけて求めた自己決定、もっと言えば自由の尊さを表現しています。
80年代当時、経済的にリッチになり、過去を振り返る余裕ができた40歳以上の主婦にとって、嫁姑との葛藤、自己決定できない歯痒さは、全て「あるある」で共感できる物語だったと思います。自己決定できない立場から、耐えて自立と成功を勝ち取る、という意味において。
このドラマを私はリアルの連続テレビで朝の時間帯に見ていました。
大抵は祖母の家で一緒に見ることが多かったのです。
祖母は毎日、このドラマを見ていました。
「おしんちゃん見ると泣けてくるんや」
「ほんまに、昔はこんなんやったんやで」
当時私はまだ学生だったので、不幸の連続の物語を見て「我慢してればきっといいことがある」というメッセージを感じ取りつつ、橋田シナリオの上手さでここぞというところは泣かされていました。
しかしドラマが終わると「ここまで不幸な人って今の日本にはいないよ」と
クールに思うところもありました。
が、しかし祖母は違います。
このドラマがきかっけで、祖母も奉公に近い住み込みで働いていたことや、実家を出て稼げるようになるまでどれだけ辛抱したかをたっぷり話してくれました。
ちなみに祖母は、おしんよりも10歳ぐらいは若いですが、同じ時代を生きてきたわけです。
高度成長期に育った私にとっては”昔話”でも、祖母にとっては、「おしん」はまさに彼女の「リアル」であり「あるある」の物語だったのです。
おしんが現代に生まれていたら
「おしん」は戦後の日本を支えてきた人にとって、共感をよべる物語なわけです。それには戦前・戦後の悲惨さを共有している、という前提があります。
じゃあ、高度成長期以降の日本人にとって、「おしん」はどう見えるのか?
これを考える前に、そもそも高度成長期以降の日本で、「おしん」って成立するのか、と考えてみました。
結論から言うと、あまり成立しない気がします。
仮に山形の最低生活の困窮世帯生まれていても、今は中学校までは卒業できる。
彼女ほどの努力家で才覚があれば、夜学にもいけるだろうし、すぐにファミレスの店長ぐらいにはなるだろう。
その後独学で簿記2級ぐらいとって、自分で商売を始めて起業できそうです。
戦後、子供の年季奉公と赤線地帯が無くなったのは大きな変化で、女性にとって確実に良い時代になっているのです。
逆に言えば、戦後日本は「劇的に悲惨なギャップや格差」がない平和な世の中で、”ドラマが作りにくい”とも言えるのはないでしょうか。(良いことですけどね)
海外の人がおしんに共感した理由
翻って、ではドラマが生まれるほどの格差やギャップはどこにあるか?といえばズバリ海外です。
80年代当時のアジア諸国、中近東ではまだ働いて仕送りをしないと食べれない世帯が大勢いたのです。
現在でもインド大都市では出稼ぎ労働者は大勢いて、コロナ渦で仕事がなくなり、地元に引き上げる時には、徒歩で帰省しているのです。
仕事で耐え、生活費を切り詰めて家族への仕送り。
どこの国であれ、出稼ぎで働く人にとって、「おしん」はまさに「あるある」でした。
こんなに小さな女の子が耐えに耐えて、家族に仕送りをしている。
そういう目で海外に人は「おしん」と自分達の生活を重ねて共感を覚えたのだと思います。