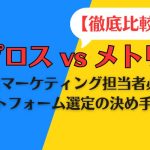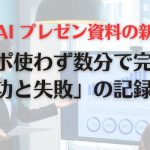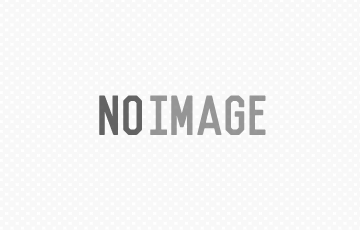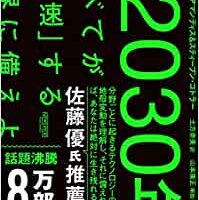生成AI(ChatGPTなど)を業務に取り入れる企業が増えています。しかし、「どうプロンプトを書けばうまく動くのか分からない」「プロンプト集をコピペしても的外れな回答しか出てこない」そんな声もよく聞きます。
そこで、本記事では、GoogleのAI Essenntialという講座で学んだことをもとに、生成AIプロンプトの書き方のコツを、「本質的な5要素」に沿ってわかりやすく解説します。
この講座は、COUSERAにあるeラーニングで通常は有料ですが、日本リスキリングコンソーシアムが今年先着1万名様限定で、新規会員登録でGoogle認定証講座の無料枠を提供してくれました。
生成AIの超大手Googleが実施している講座だけあって、要点がわかりやすく実際に使ってみると非常に役に立つものでした。B2B,B2C問わず有用だと思います。
特にマーケティングに関わる方に役立つ「ペルソナ設定」「人間による評価と改善」の重要性も取り上げます。
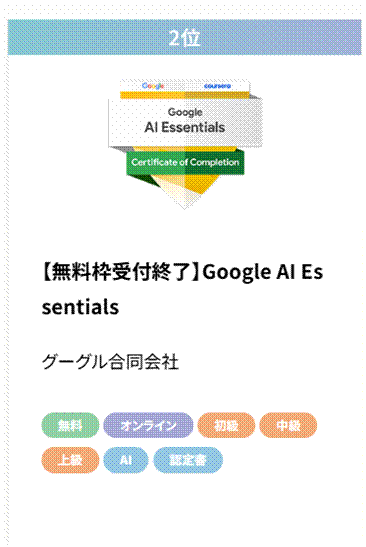
- 生成AIプロンプトの書き方コツ:本質的な5要素とは?
- 1.Task:何をどう出力してほしいかを明確に伝える
- 2.Context:文脈とペルソナを丁寧に与える
- 3.Reference:参考情報・前提知識を明示する
- 4.Evaluate:AI出力を評価するのは人間の役目
- 5.Iterate:評価して改善する──AIとの共創プロセス
- まとめ
- 生成AIプロンプトは「コピペ」では終わらない
- 定型プロンプトの落とし穴:文脈が変われば精度は落ちる
- 再利用するなら「カスタマイズ」が必須
- 生成AIプロンプトコツ:実践で差がつく具体事例
- 悪い例:ざっくりした指示だけのプロンプト
- 良い例:5要素をすべて反映したプロンプト
- まとめ:プロンプト設計は対話が基本──人間の関与が成功のカギ
生成AIプロンプトの書き方コツ:本質的な5要素とは?
プロンプトとは、AIと人間との対話をするときの作法・ルールのようなものです。正確にこちらの意図をAIに伝えるには、一定のルールがあります。
Googleの講座の中で、プロンプトの書き方のコツとして何度も繰り返されている基本は以下の5つです。
1.Task:何をどう出力してほしいかを明確に伝える
生成AIにプロンプトを入力するとき、最も大切なのは「何をしてほしいのか」を明確に伝えることです。「要約して」「記事を書いて」「比較表を作成して」等の指示です。
ここで注意したいのは、単に「記事を書いて」とお願いするのではなく、どんな目的で、どんな形式で、どんな制限で出力してほしいのかまで具体的に伝えることです。
たとえば、化粧品についてのブログ記事を書きたいとします。「この商品の魅力をブログに書いて」と依頼するだけでは、AIはさまざまな解釈をしてしまい、想定外の内容になることがあります。
しかし、「化粧品業界に精通したライターとして、この商品を紹介するブログ記事にしてください。記事は500文字以内で出力して」と伝えれば、AIは意図に近い内容を返してくれる確率が上がります。
このように、まず、何をしてほしいか(=Task)を明確に設計することが、成功の第一歩です。
次に、出力の形式(例:Markdown/HTML)、文字数(例:300文字以内)、スタイル(例:箇条書き/口語調)などの制約条件を具体的に示すことは、プロンプト設計の重要なコツです。
AIは万能ではなく、あくまで「指示に従って動くアシスタント」です。ですから指示が判りやすく、詳細であるほど期待した結果に近いものを出力します。
2.Context:文脈とペルソナを丁寧に与える
次に、「誰に向けたアウトプットなのか」「どんな前提・背景があるのか」といった文脈(Context)をしっかり伝えることが不可欠です。
ここは非常に大切です。というのも生成AIは私たちが当然と考えている「依頼の前提条件」を知りません。前提条件とは、例えば社内での情報共有の内容や暗黙知の部分です。
イメージとして、生成AIは東大・京大クラスの優秀な新卒アシスタントだと考えるとちょうどいいと思います。勤勉で非常に頭が良く、何を聞いても答えてくれますが、これまで社会に出たことがないので、社内で当然と思われている暗黙知や業界の常識を理解していません。そこをしっかりと教えてあげる必要があるのです。
前項の化粧品の例で言えば、「化粧品業界に精通したライターとして、この商品を紹介するブログ記事にしてください。記事は500文字以内で出力して」と指示するだけでは、AIは誰に何を訴求してよいか分からず、ありきたりな文章を返してしまうことがあります。
しかし、「ブログ記事は9月から11月に実施する秋のキャンペーンに使用します。キャンペーンは「美白製品」を訴求軸にします。この製品は30代前半の働く女性を対象にしています。この製品の魅力を30代女性向けに訴求するブログ記事にしてください。女性に対して印象に残る柔らかいトーンでお願いします。」と伝えれば、AIはより意図に近い内容を返してくれます。
このように、「ペルソナ(想定読者)」と「使用シーン(背景・文脈)」を明確にして、より多くの情報を与えることで、生成AIは読み手のニーズに合わせた文章を出力しやすくなります。
こうしたContextの指定は、文章のトーン・構成・用語選びすべてに影響します。
特にマーケティング分野では、「誰に向けて書くか」は売上に直結する視点なので、プロンプト内でもこの情報は欠かさず詳細に記述するようにしましょう。
3.Reference:参考情報・前提知識を明示する
次に、生成AIに期待通りの出力をしてもらうコツは、参考となる情報(Reference)を与えることです。
これは前章で説明したコンテクストを補強する意味があります。
AIに考えさせる段階で「どのような内容・文体・事例をベースにして出力するか」という参考情報を与えて、出力結果の精度を高めるのです。
たとえば、次のような指示は、Referenceが含まれている例です。
文体は、この会社の広報ブログと同じトーンでお願いします。
参考ページ:https://example.com/product123
参考URLの代わりに参考資料(pdf等のドキュメント類)を指定することもできます。
このように、リンク・過去記事・ブランドトーンマナー(トンマナ)などを提示することで、AIは、よりこちらが期待する結果に近い出力をしてくれるようになります。
特に企業ブログや販促コンテンツでは、自社らしさ・統一感が重要になるため、Referenceの指定が品質に直結します。
4.Evaluate:AI出力を評価するのは人間の役目
生成AIが返してくる出力結果は、そのまま使えるとは限りません。
むしろ、生成された内容を「そのまま鵜呑みにせず、人間がしっかり評価する」ことが必須です。
前章で、生成AIは、非常に優秀な新卒の東大・京大クラスのアシスタントのイメージとご説明しました。このアシスタントは、たまに高く評価されたいばかりに、悪意なく嘘を言ったりごまかしたりする傾向があります。
ですから、この出力結果は本当なのだろうかと常に疑う気持ちを持ちましょう。
たとえば、ブログ記事が出力されたとしても、それが本当に読者のニーズに合っているか、
自社のトンマナとずれていないか、数字や主張が事実と合っているか、を必ず人間が確認してください。
特にマーケティングにおいては、
- 言葉遣いがターゲット層に合っているか?
- 表現が強すぎないか、または弱すぎないか?
- 数字等がある場合、根拠はあるか?
といったチェックは重要です。
生成AIは、「正しい答え」や「完璧な文章」を出す存在ではなく、「そこそこ使える叩き台を素早く出してくれるアシスタント」ぐらいに捉えて丁度いいと思います。
ですから、プロンプトを投げたあとは必ず、目的に照らして出力を評価するフェーズを挟んでください。
これは人間にしかできない、生成AI活用の「品質保証」とも言えます。
5.Iterate:評価して改善する──AIとの共創プロセス
生成AIは、「出力→評価→再指示(改善)」のプロセスを何度か繰り返すことで、出力結果の精度を高めることができます。
これが、生成AIを業務で活かすうえでの最大のメリットです。
相手が人間の場合、あれこれ繰り返し指示したり、何度も細かく修正を依頼すると、大抵の場合嫌がられます。人は本来、他人に指示されるのが嫌いです。
しかし生成AIの場合、何度同じ質問をされても、何度細かいことを言われても嫌がらず、こちらが納得するまで最後まで付き合ってくれます。
多少間違ったり、ごまかしたりすることはあるものの、東大・京大クラスの優秀なアシスタントが最後まで付き合ってくれるのは大きなメリットです。
このように、出力結果を受けて、追加指示や修正をかけていく「繰り返し改善」のことを、Iterate(イタレート)と呼びます。
Iterateとは、「繰り返し言う(行う)、強調して繰り返す」という意味です。repeatは単純に繰り返す、と言う意味ですが、Iterateは、重要な点を明確にしたり、相手に強く伝えたい場合に、一度だけでなく何度も繰り返して言うというニュアンスがあります。
この繰り返し改善を、Evaluate(評価)とセットで行うことで、プロンプトの意図がより正確にAIに正しく伝わるようになります。
生成された文章を読んで、気にいらない箇所や修正したい箇所が見つかったら、再度、指示を出しましょう。例えばこんな具合です
「具体的な導入事例を1つ加えてください」
「もっと短く、読みやすい文に書き換えてください」
「先に結論を示す構成にしてください」
このように、一度出てきた出力に対して「どう直してほしいか」を伝えることで、AIからの出力結果を自分の要求にあったものにすることができます。
コツは、最初の出力結果でガッカリして終わりにしないことです。
うまく活用している人ほど、1回で満足せず、2回目・3回目で内容を磨いています。1回のチャットで生成AIと20回以上やりとりするという人もいます。
このプロセスを面倒と感じるか、共創と捉えるかで、生成AIの価値は大きく変わります。
「評価して、改善する」というプロセスで、AIは単なるツールから「一緒に働くパートナー」に進化します。
生成AIプロンプトは「コピペ」では終わらない
定型プロンプトの落とし穴:文脈が変われば精度は落ちる
最近では「最強のプロンプト○選」「ChatGPTにこう聞け!」といったテンプレート集が多く出回っています。
たしかに、プロンプトのひな形を持っておくこと自体は、業務効率化のために有効です。
しかし、そのテンプレートをそのままコピペして使うだけでは、思ったような成果につながらないことが多いのです。
なぜなら、生成AIが出力する内容は前項で説明した文脈(Context)に強く依存するからです。
たとえば、同じ「商品紹介文を書いて」というプロンプトでも、
- BtoC向けの化粧品紹介
- 官庁向けの説明資料
- 社内向けの資料用説明文
では、求められるトーンも構成もまったく違います。
しかし、定型プロンプトではそうした違いが反映されていません。このため精度の低いピント外れのアウトプットになってしまうのです。
これは、AIが「賢くない」からではありません。人間側の「指示の出し方」に、文脈(Context)が足りず、うまくいかないだけなのです。
生成AIは、テンプレート的に使うのではなく、「どの状況に最適化するか」という視点で、テンプレートを調整することが重要です。
再利用するなら「カスタマイズ」が必須
生成AIのプロンプトは、一度作ったものを再利用できます。これはとても有難いことですが、再利用する際には必ず「その都度カスタマイズする」癖をつけましょう。
SNS投稿の例で言えば、「新商品を紹介するInstagram投稿文を作る」ためのプロンプトがうまくいったとしても、別の商品の紹介や、異なるターゲット層、投稿するタイミング等が異なる場合、プロンプトの文脈や目的をきちんと入れ替える必要があります。
プロンプトのひな形があっても、「今、誰に対して」「どのような媒体で」「どんなトーンで」「いつ投稿する」かを毎回調整することが、アウトプットの質を高めるためには欠かせません。
特にマーケティングの現場では、商品の特性や読者の関心、投稿タイミングなどが違えば、「ちょっとした言葉の違い」はコンバージョンに大きく影響します。
だからこそ、カスタマイズする癖をつけておくことで、生成AIは一段と強力なツールになります。
生成AIプロンプトコツ:実践で差がつく具体事例
ここでは、これまでに紹介した5つの本質要素(Task/Context/Reference/Evaluate/Iterate)を踏まえて、実際のプロンプトの「悪い例」と「良い例」を比較してみましょう。
ここではイメージしやすいので、B2C向けの化粧品という例を考えます。
B2C領域、とくにSNS発信では「トーン」「共感性」「文字数制限」「媒体特性」などを考慮する必要があります。
このような場合、プロンプトにも媒体やターゲットに最適化された要素を明示しておくことが大切です。
悪い例:ざっくりした指示だけのプロンプト
この化粧品をInstagramで紹介してください。
- Taskだけの指示(投稿スタイルや口調形式などが不明、媒体の制限(文字数やハッシュタグ)も考慮されていない)
- Contextなし(誰に向けた投稿か?が示されていない)
- Referenceなし(どの資料・背景に基づくか不明)
- Evaluate・Iterateも想定されていない
良い例:5要素をすべて反映したプロンプト
20代後半のメイク好き女子になってください。同世代の20代後半の女性向けに、新発売の美白美容液をInstagramで紹介する投稿文を作成してください。
-友達に語りかける、カジュアルで親しみやすい口調
-最大140文字-ハッシュタグを3つ入れて
-絵文字を適度に使用
【参考】
-商品ページ:https://example.com/products/whitening-serum
-これまでのInstagram投稿例:https://instagram.com/our_brand(投稿スタイルを踏襲)
-トンマナは「等身大」「前向き」「信頼感」を大切にしてください。
- Task明確(投稿スタイルや口調形式、媒体の制限(文字数やハッシュタグ)が指定されている)
- Contextあり(誰に向けた投稿かが明示)
- Referenceあり(参考資料が明確)
- Evaluate・Iterate:作成依頼した文章が、期待した内容でなければ修正を想定している
このように、B2CのSNSマーケティングでは、「誰に向けて発信するのか(ターゲット)」「どの媒体で使うのか(チャネル)」「どんなトーンで届けるのか(表現スタイル)」
という3点をプロンプト内に明確に含めることで、AIが出力すべきイメージがぐっと明確になります。過去の投稿例も指示すると、ブランドのトンマナ(文体・絵文字の使い方など)に一貫性を持たせることができます。
では、このプロンプトに対して生成AIから以下のような投稿文が返ってきたとします。
忙しい朝でも、これ1本で透明感チャージ✨
新発売の美白美容液、使ってみませんか?
#時短スキンケア#透明肌#新商品
一見よくできていそうに見えますが、人がチェックしてみると、改善の余地が見えてきます。ここからが人間が気づきを得て、本当に考えなければならないところです。
- 実際の美容液の特徴(成分や効果)には触れていない
- ハッシュタグがやや一般的すぎて埋もれそう
- ブランドの“等身大・前向き・信頼感”というトーンが少し弱い
そこで、AIに再指示(Iterate)してみます。
ビタミンC配合、無添加処方を含めてください。
「前向きで信頼感のあるトーン」をもう少し強めてください。
ハッシュタグはブランドらしいものを3つ再提案してください。
このように具体的に改善点を伝えることで、AIはそれを踏まえて次の出力をブラッシュアップして出力してくれます。
AIはこちらが納得するまで最後まで付き合ってくれます。人間相手だと、相手の時間の都合もあるのでどうしてもこういうことはできません。
このサイクルこそが、人間とAIのコラボレーションです。
まとめ:プロンプト設計は対話が基本──人間の関与が成功のカギ
生成AIは、質問に答えるだけの「検索ツール」「時短ツール」でもありません。万能な「自動化ロボット」でもありません。
本質はむしろ、人間の意図をくみ取りながら「対話」を通じてアウトプットを一緒に作る、パートナーのような存在です。
そのために重要なのが、この記事で紹介した5つのプロンプト設計要素:
- Task:何をどう出力してほしいか
- Context:誰に向けて、どんな状況で
- Reference:どの情報やトーンを参考にすべきか
- Evaluate:人間が出力を見て評価する
- Iterate:評価に基づいて改善を重ねる
これらは単なるチェック項目ではなく、AIと価値あるコンテンツを生み出すための「会話のルール」とも言えるもので、Googleの基本コースでも何度も繰り返し強調されています。
一度出力したプロンプトを、何度か再評価・修正して育てていくプロセスこそが、生成AIをつかう醍醐味です。
繰り返し改善を重ねたプロンプトは、自分たちの業務にぴったり合った「洗練されたテンプレート」へ進化します。
こういったテンプレートをいくつも積み重ねていくうちに業務改善というのが進んでいくのだと思いました。
これからの時代、生成AIを使いこなせるかどうかは、業務改善のスピードや情報発信の質などに直結します。
ただコピペするのではなく、目的に合わせて「AIとの会話」を調整できる人こそ、職場の生産性を上げ、AI時代のマーケティングを先導する人材になれるのだと思います。
[参考資料]