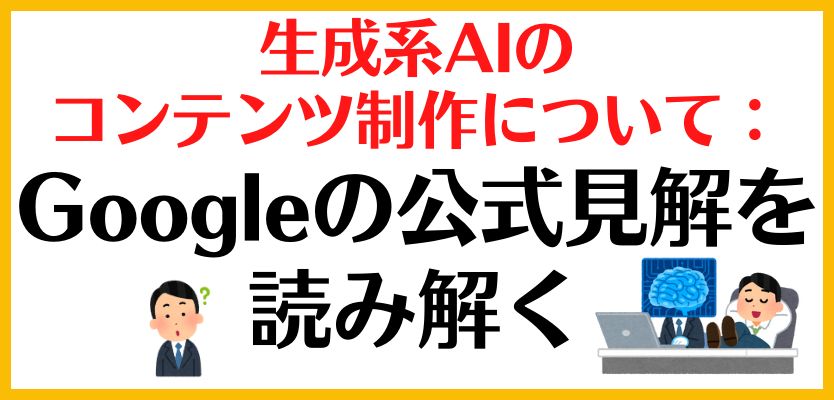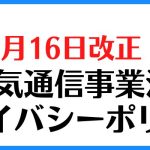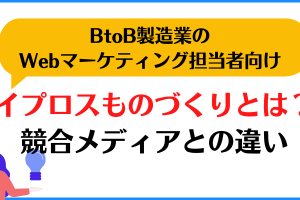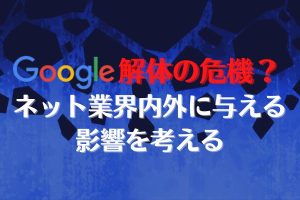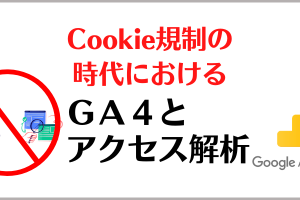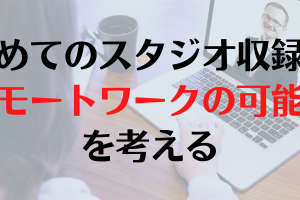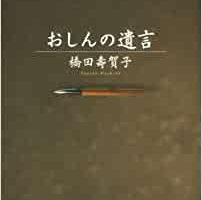最近AIの話題チャットGPTの話題で持ちきりです。コンテンツ制作や記事の見出しなどをAIで作れば楽になるという記事で溢れています。
しかし、そもそもAIを使った記事を作ったところで、逆にGoogleに見破られてペナルティを受けるのではないかと心配の方も多いのではないでしょうか。
何しろGoogleはAIの本家本元、チャットGPTの元になるトランスフォーマーというモデルを作ったのもGoogleです。AIで作った記事の癖などすぐに見破られそうです。
今日はそんな不安をお持ちの方に向けて、GoogleがAIについてどのようなスタンスを持って臨んでいるかを公式見解について解説したいと思います。
この記事を読んでいただければ、どこまで記事作成にAIを使っていいのかについて、Googleの考え方がわかり、今までのモヤモヤがすっきりすると思います。
なお、この記事でご説明している内容は全てGoogleの公式デベロッパーサイトからの引用です。
Googleは記事の制作方法を問わない
Googleは今年の2月2023年2月に、AI生成コンテンツに関するGoogle検索のガイダンスを発表しています。
この中でGoogleは、コンテンツがどのように制作されたかではなく、その品質に重点を置くと明確に述べています。
では記事の品質というのは何で決まるか。
これは従来から言われているE-E-A-T(専門性、エクスペリエンス、権威性、信頼性)の4つのポイントです。
またこれも従来から言われていることですが、ユーザーの役に立つコンテンツを第一に考え検索エンジンに好かれようとするコンテンツを避けるようにというのも明確に述べています。
Googleが自分たちのコンテンツを評価する時に見直しすることを進めているのが、
Who,How,Whyの3つのポイントです。
Who 誰が(コンテンツを作成したか)
誰がコンテンツを作成したのかが明確であれば、そのコンテンツのE-E-A-Tは直感的に理解されやすくなります。コンテンツを作成する際は、コンテンツの制作者を明確にしたり、署名記事(バイライン)にするなど、「誰が」書いているのかを明確にしましょう。

https://newspapers.ushmm.org/blog/2017/09/12/what-exactly-are-bylines/ より転載
How どのように(コンテンツが作成されたか)
コンテンツがどのように作成されたかをGoogleは重視する、と言っています。
例として商品レビューを挙げてしますが、これはどれだけ根拠のない商品レビューが氾濫しているか、とういことの裏返しでしょう。AIを使ってコンテンツを作ったかどうかについても、明示するとことが望ましいとされています。(そんな人だれもいないでしょうが)
ただ、現在のAIの進化のスピードを見ていると、偽の商品レビュー等をつくるのも朝飯前という気がしています。自動生成された虚のテスト画像等をどこまで見破れるのかは疑問が残ります。
反対に、自社でテスト環境やデモルーム、試験環境、スタジオ等を持つ会社や個人の方は、積極的に情報を公開すれば、自社独自のコンテンツとして高く評価される可能性が高くなります。
Why なぜ(コンテンツが作成されたか)
そもそもなぜ、コンテンツを作成したのか。
この「なぜ」に対する答えを明確にすることも大事になってきます。そうすることで、サイトを直接訪れた人々にとって有用なコンテンツかどうかが判断しやすくなるからでしょう。これは、利用者の役に立つコンテンツを表示したいというGoogleの方針にもあっています。
これら3つは、ユーザにとって有用なコンテンツとして評価されるのに大事なポイントになります。
結論としては、GoogleはAIのコンテンツ制作における利用というものを、制限していません。使う側のモラルに任せています。
質の高いコンテンツを使う製作するためには使ってもらっても構わないという姿勢です。AIや自動化は、適切に使用している限りはGoogleのガイドラインの違反にならないと明確に述べています。むしろ製作されたコンテンツの質を重視するという姿勢です。
反対に、検索エンジンのアクセス数を増やすためにAIで自動生成されたコンテンツを多用する場合には、Googleのスパムに関するポリシーに違反していると見なされます。
質の低いAI生成コンテンツをどうやって防止するのか。
コンテンツ制作にAIを使って良いとなると、誰でも考えることは同じです。
プロンプトを使ってコンテンツを書こうという人が増え、大量に似たようなコンテンツが溢れるのではないか。現に今でもそうなりつつあり、似たようなまとめコンテンツが溢れ、検索結果の正しさが疑われているような状態です。
これはGoogle側の大きな課題です。しかし、Google側では従来の対策と変わらないという「自信?」を見せています。
つまり、質の低いコンテンツは、人間が作ろうが、AIが作ろうが変わらなく、これまで世の中に溢れているということです。
Googleはそのために、毎年何度も検索のアップデートを繰り返してきているわけです。

https://yoast.com/google-algorithm-updates/ より転載
2011年のPanda、2012年のPenguinの時には、SEO対策業者がバタバタと潰れました。
これから検索エンジンはBardを入れて大きく変わってゆきます。
あらためて、E-E-A-T(専門性、エクスペリエンス、権威性、信頼性)が大事になってくると思います。
ヘルプフルコンテンツシステム
AI自動生成コンテンツに関連して、最近特に注目したいのがこのヘルプフルコンテンツシステムです。
人間が、人間のために作成した独自性のある有用なコンテンツが検索結果に表示されやすくなります。
価値がほとんどないように見えるコンテンツ、価値の低いコンテンツ、ユーザーにとって特に有用でないコンテンツは自動的に識別されます。
このランキングシステムの怖いところは、「低品質コンテンツ」だけが影響をうけて表示順位がさがるのではなく、有用でないコンテンツを比較的多く含むと判断されると、ウェブ上の他のコンテンツを優先して表示すべきとして、サイト全体にペナルティが及び、検索での掲載順位が下がることです。対応策として、「有用でない」と見なされたコンテンツを削除するしかありません。
ですので生成系AIを使ってコンテンツを制作する際には、プロンプト入力して、出力されたものを安易にコピーするということは、避けた方が良いでしょう。
どういったコンテンツをどういう章立てで書くかという構成を考え、そのための論文や素材を効果的に探すという使い方であれば、生成系AIを使用して意味のあるコンテンツを作ることができると思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
Googleが公式に生成系AIによるコンテンツ制作をどう考えているかを見てきました。
生成系AIを使うこと自体には、ペナルティはありません。真っ当なコンテンツを制作することに集中してくれ、と言ってくれているわけですから、活用するべきところはどんどん活用するべきだと思います。
しかしAIが出してきた答えをそのまま鵜呑みにしてCOPY&PASTEするのは、おそらく危険です。世の中に同じようなことを考えている人は案外多く、AIに尋ねれば、結果も同じようなものになります。
やはり、最後の一捻りは人が考えて修正するというステップを忘れてはならないと思います。そして、最初の構成部分をしっかり考え、AIに助けてもらってリサーチに時間をかけるというのがよいのではないでしょうか。
以上 これからSEO対策を検討されておられる方の参考になれば幸いです。