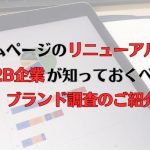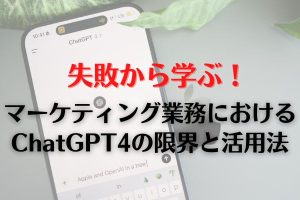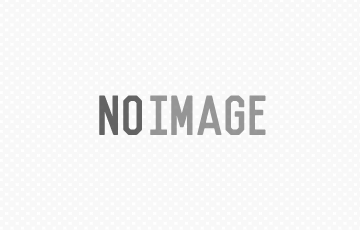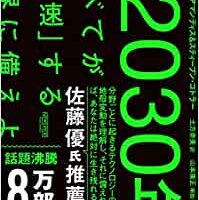ホームページで有効なリードを集められたと仮に集められたとしても、その後案件化に持って行き商談から受注に結びつけるのは並大抵ではありません。
会議や社内調整を効率化したり、議事録作成を楽にしたり、入力の手間を省いたりするのにAIは既に活用されています。
獲得したリードの中で訪問すべき優先順位を決めてくれる営業支援AIも登場しています。
でも最後のクロージングは人間がしなければいけません。
営業マンのトークのスキルを高めるためのAIはないのでしょうか。
今回は営業スキルを高めるためのAIということについて調べてみました。
ちなみに私自身も、業界はITに限られていますが、法人営業の経験が10年程、コールセンター関連の企業に3年程在籍したことがあります。
それらの経験を基に、本当に使い物になるかどうかを考えながら調べてみました。
AI×営業力:どんなことができそうか
一言でAIを使った営業支援ツールと言いますが、実にいろいろなものがあります。ここでは、第一線で顧客と向き合う営業担当のトークスキルを向上させるのに役立ちそうなものをイメージしています。
主な機能
AIで営業担当の個々人をどのように支援をしてくれるのでしょうか。主に以下のような機能が備わっているサービスが多いようです。
録画・分析
実際の商談現場を録画し、それをAIで分析してくれる機能です。
クロージングの時の成功パターンや失敗パターンを特定し、それぞれの営業担当の強みとか弱みを見つけてくれるという機能です
ロールプレイ
営業担当には、多くの会社でロールプレイという研修が行われています。かなり度胸がつきますが、残念ながらロールプレイには相手がいります。しかし、上司や先輩がロールプレイの相手になってくれるという時間もなかなか取れません。そんな時に便利なのがAIがロールプレイの相手になってくれる機能です。
フィードバック
ロールプレイの後、録画したデータからAIが自動採点し、フィードバックもしてくれます。それぞれの営業マンのトークの改善点を指摘してくれたりします。
ロールプレイをやりたいけれど、上司や先輩相手では恥ずかしいという方も多いと思います。そういった方にはこのようなAIは使い勝手がよさそうな気がします。
主要な製品
では具体的にどのような製品があるのでしょうか。
1)Gong.io
2015年の創業、米国サンフランシスコの会社です。AmitBendov氏,EilonReshef氏が共同創業しました。
通話録音、書き起こし、AIによる洞察、解析したデータをCRMに統合できる「会話分析プラットフォーム」です。
音声認識のモデルは言語を問わず動作し、営業チームは見込み客や顧客とのやり取りを詳細に記録することができます。
すべての会話が文書化され、分析用データとして活用されます。
この会社の製品は最初から、音声での記録をCRMと統合して管理するように考えられています。
最初に営業がコンタクトを取ってから、フォローアップの電話、それ以降のコンタクトから最後に受注に至るまでの取引を全てCRMで可視化することを目指しています
Hubspot,LinkdIn,SurveyMonkeyなどの有名企業が導入したので有名です。
価格面ですが、企業規模に応じて価格は変わるようです。1ユーザーあたり年間1,600ドル(25ユーザーの場合)で、3年間このシステムを利用した場合のコストを総費用は13万2500ドルという試算があります。

2)Chorus.ai
Gong.ioと競合製品です。こちらも2015年に設立された会社です。社長(前CEO)のRoyRaanani氏、CTOのRussellLevy氏、そして退社したMichaBreakstone氏によって創業されました。
2021年にZoomが買収し、現在の社名はZoominfoです。社長は米国人のJimBenton氏です。
オンライン商談をAIが記録し、分析します。商談中の会話内容から、どのタイミングでどのような内容のオファーをすると成約確率が上がるのかを可視化したり、過去データから成約率の高い商談の流れをテンプレート化して、営業人材の育成に役立てることができます。
Salesforceとの連携も可能で、同社によると営業のパフォーマンスは30%ほど向上するとのことです。
Chorus.aiは価格を未公開です。正確な見積もりには直接相談が必要で、無料トライアルはありません。
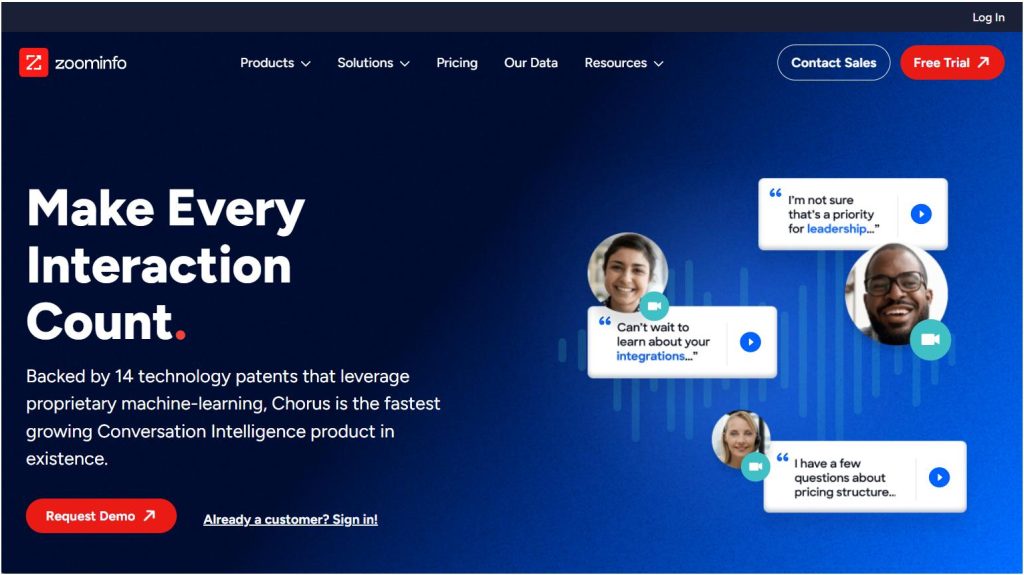
3)UMU(ユーム)
こちらも2015年創業の米国ポートランドの会社です。開発者兼創業者ドングショー・リー氏です。
この方は、元々Google社のトレーナーです。
UMUの由来は、「U(あなた)、Me(私)、Us(私たち)」の頭文字で、誰もが講師になり学び合う世界の実現を目指すラーニングプラットフォームを目指しています。
マイクロラーニング・ビデオ会議・ライブ配信・AIコーチング等の機能で、双方向性のあるオンライン学習プログラム設計ができるシステムを、SaaSで提供しています。
このプラットフォームの機能の1つに、営業担当自身が自分を可視化できる「AIコーチング機能」が実装されています。
世界203の国と地域で、100万社以上で導入実績があります。日本では、日本生命、パナソニック、アステラス製薬、ワコールをはじめとする約1万社以上がUMUを導入しています。日本の人事部HRアワード等受賞多数です。
料金は公開されており、無料お試し利用も可能です

4)AmiVoiceSF-CMS
こちらは日本の会社で、株式会社アドバンスト・メディアのサービスです。
1997年創業のIT企業で、発足当時から音声認識を手掛けており、AI音声認識分野では日本ではトップシェアです。
議事録の作成支援や医療分野での多数の導入実績があり、東京都の議事録の作成にも採用されています。
この音声認識の技術を活用して営業のトークスキル向上を支援するAmiVoice®RolePlayは2023年9月にリリースされました。
音声認識で商談や接客の会話すべてをデータ化して、自動分析し、顧客とのやりとりから、隠れた課題を発見して次につなげようというツールです。
動画内の顧客役に向かって話すため、これまで管理職やトレーナー層が必要だった相手役を行う必要はありません。いつでもどこでも任意のタイミングでセルフロールプレイングができるようになります。さらにAIを用いて実践的な反復練習ができます。
また、優秀者のトークを収集し、顧客満足・契約率向上に繋がるセールストークを可視化することで、チーム全体の営業力向上を実現します。
価格は非公開で、見積もりには直接連絡が必要です。
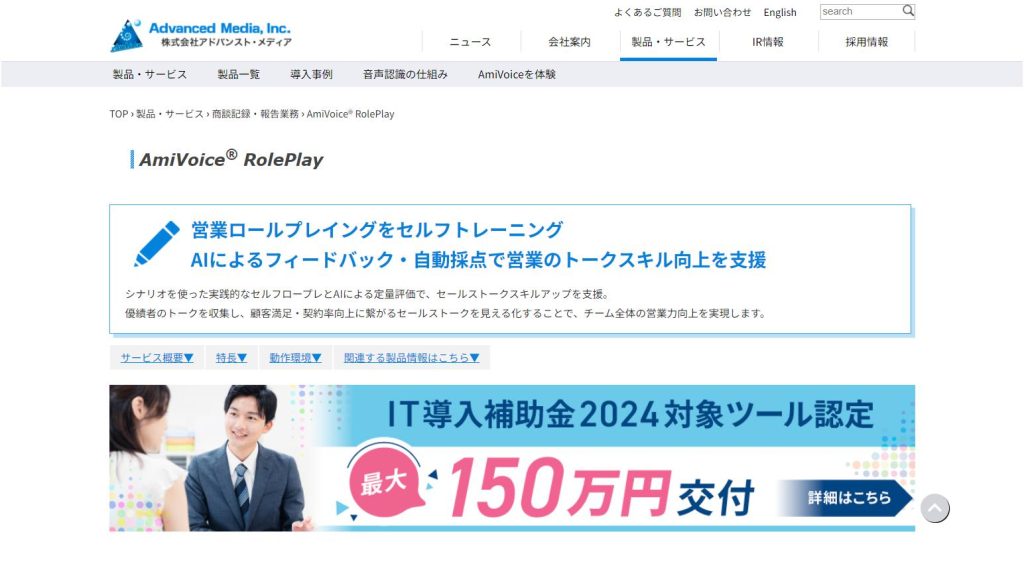
5)CallAnalytics
株式会社SceneLiveは2011年創業、本社は大阪です。
アウトバウンドに特化したコールシステムを作っているベンチャーですが、アウトバウンドのコールの成果を最大化するために、2022年10月にAI音声解析システムの「CallAnalytics」をリリースしました。
こちらも通話内容をテキスト化し、AIによる音声解析で通話の質や効果を可視化します。
音声の波形データやスピード、話者の比率などを数値化し、解析して、改善すべき点や行動指示を提供してくれます。
結果はオペレーター自身がセルフチェックで確認でき、可視化されるためモチベーションアップにもつながるでしょう。
もちろん通話内容は音声認識によって、リアルタイムでテキストデータ化されているので、あとから内容を確認できます。
アウトバウンドコールとは、オペレーターと呼ばれますが、やっていることはほぼ営業と同じく電話での営業です。自分の成績がダイレクトに収入に跳ね返ってくるという評価方式をとっているところも多いため、オペレーターの方も非常に勉強熱心な方が多いと思います。
ただし、これはアウトバウンドのコールシステムであるListNavigator.のオプションサービスになります。ListNavigator.の価格はオプション費用も含めて公開されています。
1ブース月額5000円で、同時に稼働するブース数に応じて課金される料金です。無料体験サービスがあります。「CallAnalytics」はオプション費用として一式5万円です。

以上5つですが、3つは海外のサービスです。海外のサービスはCRMとの連携やトレーニングという課題の解決にフォーカスした製品です。
一方で日本の製品は、コールセンター向けに入力コスト削減という課題からスタートしている製品が多いです。ここには取り上げませんでしたが、コールセンター向けの音声認識サービスはたくさんあります。
日本で営業のトレーニングや営業トーク力アップというところに焦点を当てた製品が出たのは2022年以降です。これはコロナによりオンラインの営業が一般的になってきたというところもあるのだと思います。
音声認識の場合、日本語会話における独特の「沈黙」「無言」をどの程度正確に評価できるのかは非常に気になるところです。このあたりは実際に試してみないと分からないでしょう。
まとめ
営業とAIを組み合わせたソリューションはITやベンチャーの業界の界隈では、セールステック領域と呼ばれています。
これまで「セールステック」はユーザーとのエンゲージメントをどうやって強めるかというのが課題で、MA(マーケティングオートメーション)というツールはそのために進化してきました。
これに加えて、音声を含めた録画という情報を新たにデータとして活用した新しいソリューションが出てきています。
営業の実際のシーンを録画し、分析をして営業の結果につなげるというところは共通しています。
しかし、日本の営業マンの場合、自分が顧客と折衝しているシーンを動画で撮影すること自体を嫌がる担当が多いのではないでしょうか。営業日報も入力しない社員がまだ多い日本企業で、このやり方が定着するのはまだ先のような気がします。
ただ、どの企業も悩んでいるのは、「個人芸」になってしまっている営業のノウハウやスキルをどうやって他の人に展開していくかということです。
トレーニングやスキルアップにつなげるのに動画を使うというのは、ノウハウを新入社員や中途採用の社員の方に移転するのに大いに役立ちます。
そういった意味ではMAマーケティングオートメーションなどのリード獲得よりも、トレーニング向けの動画の活用は、営業全体に対してはインパクトのある施策かもしれません。
目に見えない営業の知識やノウハウを見直すのは良い機会にはなるのではないでしょうか。