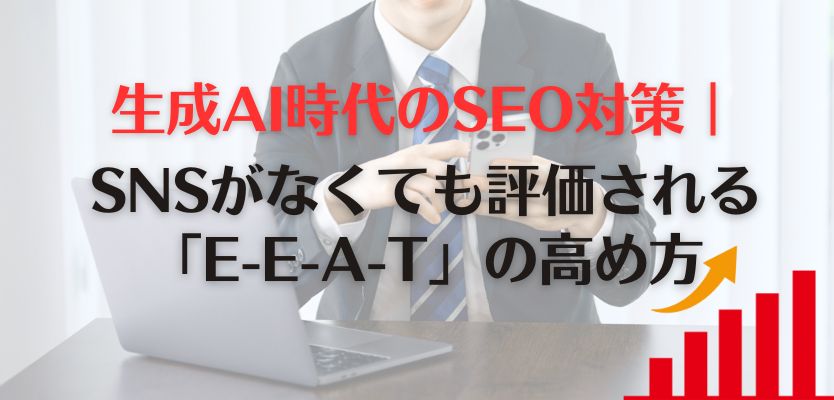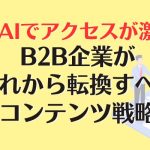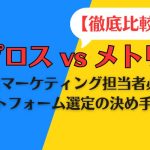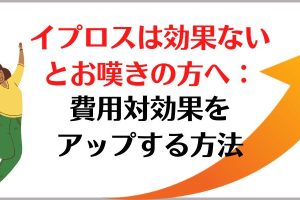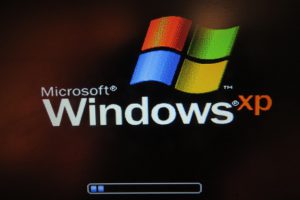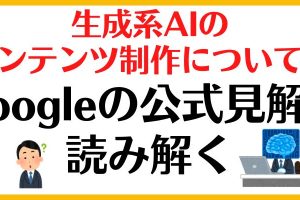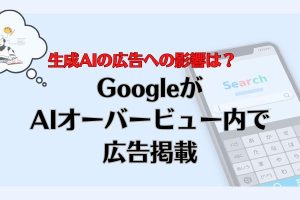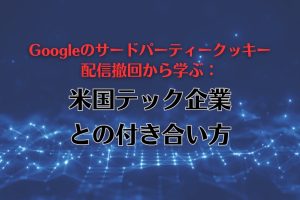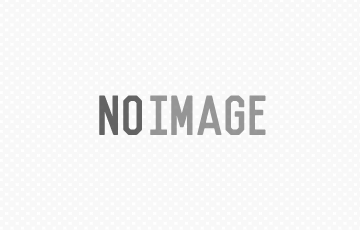生成AIの台頭によって、検索結果ページに掲載されるには「情報の正確さ」もさることながら「発信者の信頼性」が重視されるようになっています。
特にGoogleが重視する概念「E-E-A-T(Experience・Expertise・Authoritativeness・Trustworthiness)」は、 AIが生成した無数のコンテンツの中から『誰を信頼すべきか』を判断する基準になっています。
しかし、普通の企業に勤務している方で、世間に名前が知られている有名人はまれです。
SNSで名前が知られている方もいますが、個人で運営しているケースが多いです。
では、有名人もおらず、SNSで情報発信もしていない企業が生成AI時代でもSEOで評価されるために、E-E-A-Tをどう高めればいいのでしょうか?
この記事では、Googleの公式ガイドラインをもとに、オフライン実績をSEO価値に変える具体策を解説します。
- SEOとE-E-A-T|Googleが評価する信頼のフレームワーク
- E-E-A-Tとは何か? ― Googleが求める“信頼の4本柱”
- なぜ今E-E-A-TがSEOで重視されるのか
- E-E-A-TはB2B企業のSEO対策の“差別化軸”になる
- まとめ:E-E-A-Tは“信頼を伝える仕組み”
- オフライン活動はGoogleが直接把握できない
- Googleは“現実世界”を直接見れない
- オフラインでの実績を「オンラインシグナル」に変換する
- E-E-A-Tを補強する「可視化の設計」
- SNSを使わなくてもできるE-E-A-T強化策
- (1)著者・企業情報を明示し「誰が発信しているか」を明確にする
- (2)ホワイトペーパー・技術資料で専門性を可視化
- (3)プレスリリースで第三者シグナルを創出する
- E-E-A-T強化の鍵は「構造と一貫性」
- 「信頼」と「実績」で評価される
- 生成AI時代に成功するコンテンツ作成
- AI生成は「下書き」、人間の経験が「価値」
- 現場の声・一次データを反映する
- 構造化データでGoogleに正確に伝える
- まとめ:AIは全自動化ツールではない
- まとめ|E-E-A-Tの強化に向けて
SEOとE-E-A-T|Googleが評価する信頼のフレームワーク
E-E-A-Tとは何か? Googleが求める『信頼の4本柱』
最近の検索アルゴリズムは、「どれだけ情報量が多いか」よりも「誰が、どんな経験から語っているか」を重視するようになりました。
その基準が、Googleが定義するE-E-A-T(Experience・Expertise・Authoritativeness・Trustworthiness)です。
- Experience(経験):実際の体験や実務知識に基づいた発信か
- Expertise(専門性):分野の専門知識や資格を持つ人による内容か
- Authoritativeness(権威性):業界・第三者・他媒体からの信頼があるか
- Trustworthiness(信頼性):正確な情報を、透明な運営主体が提供しているか
これらは検索順位を直接決定する「スコア」ではありません。
ただし、GoogleがAIを使って膨大な情報を評価する際の『品質評価のフレームワーク』として、最も重要な概念になっています。
なぜ今E-E-A-TがSEOで重視されるのか?
AI時代のSEOでは、「文章をいかに早く量産するか」よりも、“誰が書いたか”と“何に基づいているか”が問われます。
Googleの公式ブログでは次のように述べています。
“Using AI doesn’t give content any special gains. It’s just content. If it is useful, helpful, original, and satisfies aspects of E-E-A-T, it might do well in Search. If it doesn’t, it might not.”
(AI を使用したからといってランキングに関して特別なメリットがあるわけではありません。有用、有益なオリジナル コンテンツで、E-E-A-T の基準を満たすものは、検索で上位に表示される可能性が高くなります。作成方法ではなく、内容が評価の対象となります。)
— Google Search Blog, 2023/02
つまり、Googleは、「生成AIで書いたから評価されない」という立場ではなく、独自性、有用性を重視しています。
ここで重要なのが、E-E-A-Tの最初のE(Experience)です。
「実際に手を動かした」「現場で検証した」「顧客と対話した」 こうしたリアルな経験に基づく発信は、AIでは代替できません。だからこそ信頼性の根拠になるのです。
E-E-A-TはB2B企業のSEO対策の差別化軸になる
特にB2B領域では、製品の技術情報や事例紹介など、“一次情報”を持つ企業ほどE-E-A-Tで優位に立てます。
なぜなら、検索エンジンは企業自身が発信する技術レポート・導入事例・展示会情報などを
「発信者による証拠」として評価するからです。
たとえば、
- 自社エンジニアが執筆する技術コラム
- 実際の導入プロジェクトに基づいた事例ページ
- 製品開発の裏側を説明するホワイトペーパー
これらのコンテンツは、一般的なAI生成文よりも信頼性が高く、 Google 検索品質評価ガイドライン(Google Search Quality Evaluator Guidelines)によって「専門家による一次情報」として高く評価されます。
Google 検索品質評価ガイドラインとは、Googleが社外の品質評価者向けに公開しているマニュアルです。Googleが契約する品質評価者向けに、約200ページにも及ぶガイドラインを公開しています。このガイドラインは、Googleがどのような要素を重視しているかを示す貴重な資料です。
検索品質評価基準については、こちらに詳細をまとめていますのでご覧ください。
まとめ:E-E-A-Tは『信頼を伝える仕組み』
生成AI登場以降のSEOの本質は、キーワードを詰め込むことではなく、Googleが理解できる形で信頼を表現することです。
E-E-A-Tは、その信頼を検索エンジンの言語に変換し、伝えるための品質評価フレームワークです。
そして、生成AI時代の今こそ、人の経験・専門知識・実績をどう伝えるかが、B2B企業のSEOの成否を分ける最大の要因になります。
オフライン活動はGoogleが直接把握できない
Googleは『現実世界』を直接見られない
B2B企業の多くは、展示会、専門誌への寄稿、学会発表など、こうしたオフラインの場で長年にわたり信頼を築いてきました。
ただし、Googleの検索アルゴリズムは、これらの活動を直接認識することができません。
Googleのクローラーは「ウェブ上に存在するテキストや構造化データ」を通じてのみ情報を理解しているからです。
つまり、どれほど優れた講演や受賞歴があっても、それがオンライン上に『確認可能な形』で存在しない限り、検索評価には反映されません。
検索エンジンは、オフラインの活動がそのまま評価するのではなく、オンライン上で観測可能なシグナル(ページ、リンク、言及)を通してのみ権威や評判を推定できるのです。
オフラインでの実績を『オンライン・シグナル』に変換する
では、展示会や出版、専門誌への寄稿といったリアルな実績を、どうすればGoogleに伝えられるのでしょうか?
ポイントは、オフライン活動を『オンラインで検証可能な情報』に変換することです。
具体的なアプローチは、例えば次のような方法です。
- 展示会・セミナーの出展情報を「ニュース」や「導入事例」として公開する
- 業界誌・メディア掲載を「お知らせ」や「掲載情報一覧」としてまとめる
- 講演資料・技術パンフレットをPDFやHTMLで公開し、検索エンジンにインデックス登録させる
こうした工夫を、Googleは「実績の裏付けがある企業」として評価します。
逆に言えば、リアルな世界での権威性も、E-E-A-Tの『Authoritativeness(権威性)』をつけるには、オンライン上の再現可能な証拠によってしか獲得できないのです。
E-E-A-Tを補強する「可視化の設計」
SEOの世界では『リンクは信頼の投票』とよく言われます。
例えば、オフラインの活動がニュースや業界ポータルで紹介されることで、自然な被リンクやブランド検索が発生します。
それこそがE-E-A-Tの要となる「信頼シグナル」です。
Googleは企業の現実世界での活躍を直接見ているわけではありません。
しかし、その活動を正しくオンラインに翻訳し、Googleが理解できる形式(構造化データなど)で示すことは、どの企業でも可能です。
展示会、専門誌、講演といったリアルの積み重ねを、検索エンジンが理解できる「信頼の証拠データ」変えることが重要です。この『翻訳作業』が、B2B企業が生成AI時代のSEOで成果を出すための出発点です。
3. SNSを使わなくてもできるE-E-A-T強化策
現実の世界をオンラインに反映させるために、やはりSNSで日々の企業の出来事を発信しなくてはならないのでしょうか。
ネットマーケティングの世界では、「SNSを活用しなければ認知が広がらない」「発信頻度が高いアカウントが有利」といった声を耳にします。
もちろんSNSは、信頼性や権威性の獲得には有用です。しかし、GoogleはSNSのフォロワー数や投稿頻度を直接的なランキング要因としていません。
検索アルゴリズムが評価しているのは、「オンライン上で確認できる信頼の証拠」つまりシグナルです。
SNSはそのシグナルの一部にすぎず、E-E-A-Tを高めるための道は他にもいくつも存在します。ここでは、「SNSなしでもできる」現実的なE-E-A-T強化法を3つ紹介します。
(1)著者・企業情報を明示し「誰が発信しているか」を明確にする
E-E-A-Tの「Trust」と「Experience」を高めるには、発信者情報の透明化が不可欠です。
B2B企業の多くは記事を「無署名」で公開していますが、これは信頼の損失につながります。
以下の3点を実装するだけで、Googleが発信者を「実在する専門家」として認識しやすくなります。
- 記事やレポートに執筆者名と経歴・所属部門・専門分野を明記する
- 会社概要ページに所在地・代表者・設立年・事業内容を明記し、問い合わせ先を明示することにより実在性を担保
- これらの情報を構造化データ(Organization/Person schema)でマークアップする
これにより、Googleの品質評価者やAIが「信頼できる実体による発信」と判断しやすくなります。
その結果、検索エンジンや品質評価者は「誰が」「どの立場で」「どんな経験に基づいて」情報を発信しているかを理解できます。
特にB2Bでは、個人よりも企業全体としての信頼構造を示すことが効果的です。
(2)ホワイトペーパー・技術資料で専門性を可視化
SNSよりも持続的で評価されやすいのが、ホワイトペーパー(技術資料・導入事例)です。
これは、Googleが実務に基づいた経験やデータを重視しているためです。
現場データや事例を含む技術資料は、E(Experience)とE(Expertise)を裏付ける強力な証拠になります。
Googleは「人の経験や実務データに基づく一次情報」を高く評価しており、技術資料・導入事例等はまさにE-E-A-Tの『E(Experience)体験』と『E(Expertise)専門性』を裏付ける最適な形式です。
- 導入事例をPDFやHTMLで公開し、検索エンジンにインデックス登録させる
- 製品比較や技術解説のコラムに、社内実験データや写真、検証結果を掲載する
- ホワイトペーパーをランディングページ(LP)で紹介し、関連キーワードで流入を狙う
これらは単なる資料ではなく、実際に体験した証拠をオンライン上で可視化したコンテンツです。AI生成コンテンツにはない「信頼の厚み」を検索エンジンに伝えることができます。
(3)プレスリリースで第三者シグナルを創出する
SNSの代替として最も効果的なのが、プレスリリースの活用です。
プレスリリースは、自社がニュース性を持つ活動を行っていることを示す第三者的な信頼シグナルになります。
昔のプレスリリースと異なり、今はオンライン上で手軽にできるプレスリリース媒体がいくつもあります。知名度が高いのは「PR TIMES」ですが、それ以外にも無料配信に対応する媒体もあります。
プレスリリースというと大げさに考えがちですが、ネタはいくつもあります。
| オフライン活動 | オンラインでの可視化方法 | 検索エンジンに伝わる効果 |
| 展示会出展 | イベントレポート | ニュース性・専門性の強調 |
| 業界誌掲載 | 掲載情報ページ、引用リンク | 第三者評価の証拠 |
| 講演・セミナー | 講演資料PDF、登壇情報 | 実務経験の提示 |
| 受賞・認定 | 受賞歴ページ、審査機関へのリンク | 権威性・信頼性の裏付け |
これらのプレスリリースや業界ポータルサイトに掲載されると、Googleはこうした言及を観測可能なシグナルとして評価し、企業の権威性を補強します。
- プレスリリースメディアからのナチュラルリンク(被リンク)の発生
- 各種メディアのニュース枠への掲載
- 企業名+製品名の関連検索
といった複合的なSEO効果が期待できます。
SNSを毎日運用できなくても、プレスリリースは「企業発信の信頼できるデータ」をウェブ上に残す有効な手段です。
E-E-A-T強化の鍵は「構造と一貫性」
このように、「現実の信頼」を「ウェブ上の構造」に変換する行動が、自社のE-E-A-Tを支える基盤になります。
ここまでの施策はいずれも、以下のポイントを明確にすることは共通しています。
- 誰が書いたか、透明性が確保されているか(Transparency)
- 体験や実務知識に基づいた根拠がある発信か(Experience)
- 業界・第三者からの信頼があるところで言及されたか(Authority)
SNSのように流れていってしまう情報は、拡散には向いていますが、B2Bサイトに求められるのは長期的に蓄積される「信頼」です。プレスリリースや企業公式の「静的ではあるが長く残る発信」はGoogleの評価に直結します。
記事、資料、プレスリリースといった各要素を互いにリンクさせることで、Googleから「専門性のある組織的発信」として評価されることが期待できます。
「信頼」と「実績」で評価される
SNSを更新できなくても、検索評価は高められます。
重要なのは、「専門家としての経験」と「企業としての信頼」をオンライン上で一貫したシグナルに変換することです。
- 著者・企業情報を明示して透明性を担保する
- ホワイトペーパーや事例で経験を裏付ける
- プレスリリースで第三者の信頼を可視化する
- デモや事例解説の動画を公開する
これらを積み重ねることで、Googleが理解できるE-E-A-Tの「信頼構造」が形成されます。
SNSで発信量を競うのも大切ですが、一方でこれまで蓄積してきた『見えない信頼を可視化する』工夫を積み重ねる方が、AI時代にB2B企業が取るべき戦略として本質的です。
生成AI時代に成功するコンテンツ作成
人間の体験や経験をGoogleに伝えるように変換すればよいということはわかりました。では具体的にどのようにコンテンツを作ればよいのでしょうか。
AI生成は「下書き」、人間の経験が「価値」
ChatGPTやGeminiなどの生成AIは、構成案や要約の自動生成に非常に長けています。
しかし、AIが出力する文章は正確に見えるが根拠がないことも多く、E-E-A-Tの観点では「Experience(経験)」と「Trust(信頼)」が欠けています。
Googleも次のように明言しています。
“Automation has long been used in publishing to create useful content. AI can assist with and generate useful content in exciting new ways.”
(自動化は有用なコンテンツを作成するために制作の現場で長い間使用されてきました。AI を活用することで、これまでにない面白い方法で有用なコンテンツを作成したり、コンテンツをさらに改善したりできます。)
— Google Search Blog,(2023年2月)
AIが文章の骨格を作り、人間が「信頼の肉付け」を行うというハイブリッド構成こそが、B2B企業が生成AI時代に信頼を得る鍵だと言えるでしょう。
現場の声・一次データを反映する
Googleの品質評価ガイドラインでも、「first-hand expertise(一次的な専門知識)」が高品質ページの特徴として挙げられています。
生成AIでいくら流暢な文章を作成しても、実際の検証データやユーザー事例がなければ「独自性(originality)」が不足します。
AIに初稿を生成させた後、社内の技術者・研究者が自らの経験や実測データを追記する工程こそ、E-E-A-Tを高める最短ルートです。
実務で効果的な一次情報の例
- 製品比較:競合製品との性能差や導入コストの実測データを記載
- 実験レポート:温度・照度・耐久性など、実験条件と結果を明記
- 導入事例:顧客企業の課題と改善効果を具体的に記載
これらを組み込むことで、AIには生成できない“現場のリアルをGoogleに伝えられます。
現場データを取り入れることは、アルゴリズムに信頼の根拠を示す最も直接的な方法です。
構造化データでGoogleに正確に伝える
人間の経験をいくら文章に書いても、Googleがそれを正しく理解しなければ評価に結びつきません。
その「理解を助ける翻訳装置」が、構造化データ(Structured Data(schema.org))です。
構造化データを使うと、Googleはページ内の意味を明確に把握できます。
特に次の3つは、B2B企業のE-E-A-Tを補強する代表的な要素です。
- Person:著者や監修者の情報(役職・資格・経歴など)
- Organization:会社の公式情報(所在地・ロゴ・連絡先)
- NewsArticle:プレスリリースや技術発表などのニュース型コンテンツ
これらをHTML内にJSON-LD形式で埋め込むと、Googleが発信者を「実在する企業・専門家」として正確に理解できるようになります。
まとめ:AIは全自動化ツールではない
AIは、人の代わりに書くものではなく、人の知見を広げる補助ツールです。
全自動化してくれるツールというよりも、共に創る共著者として扱うのが適切だと言えます。
AIのスピードと網羅性を活かしつつ、人間の経験と倫理を加味することで、E-E-A-Tを備えた真に価値あるコンテンツが生まれます。
- AIで下書きを作り、専門家が実務データで補強する
- 現場の一次情報を活用して『信頼できる独自性』を出す
- 構造化データでGoogleに「誰が・何を・なぜ書いたか」を正確に伝える
AIで作った下書きを、人間の経験で補足し、構造化データで検索エンジンに正しく伝える。これが、生成AI時代における信頼を獲得するコンテンツ制作のコツと言えるでしょう。
まとめ|E-E-A-Tの強化に向けて
AIが進化する今、SEOの主戦場はキーワードの最適化ではなく、企業の信頼をどのように『構造化して伝えるか』に移りつつあります。
企業がE-E-A-Tを強化するには「実績の可視化」と「継続的発信」が不可欠です。
オフライン実績は「オンライン化」して初めて評価されます。
展示会出展、メディア掲載、講演実績などといったオフラインの活動は、そのままではGoogleに届きません。
しかし、プレスリリースや事例記事としてウェブ上に記録することで、「オンライン・シグナル」として検索評価の入口になります。
オフラインの信頼をデジタル上で再現すること。これが、AI時代のE-E-A-T戦略の第一歩です。
SNSはあくまで拡散の手段の一つにすぎません。公式SNSは運用した方がよいですが、SNSがなくても信頼を作ることはできます。
B2B領域では、プレスリリース・技術資料・導入事例といった『長期的に残る信頼コンテンツ』が重要です。
これらは、Googleが評価する第三者的な信頼シグナルを生成し、企業の専門性や継続的な活動を裏付ける証拠になります。
信頼は「一度作って終わり」ではなく「蓄積される資産」です。
E-E-A-Tの評価は一過性ではありません。Googleのアルゴリズムは、過去の情報発信や外部からの言及などを総合的に参照し、時間をかけて信頼を積み上げる企業を評価する仕組みです。
だからこそ、B2B企業にとって重要なのは「継続的な発信」です。
定期的にプレスリリースやホワイトペーパーを更新し、自社サイト上で『専門性の履歴』を積み重ねることが、長期的な検索評価の安定につながります。
生成AIの時代こそ、「実在する専門家」「実在する企業としての発信」は最も強いSEO戦略です。
AIが生成する大量の情報の中で、信頼できる一次情報を持つ企業は重視され、長期的に評価されます。
企業が持つ経験・技術・成果を、Googleが理解できる構造でどう可視化するか。
それが、今後のSEOとE-E-A-T対策の本質です。
[参考資料]